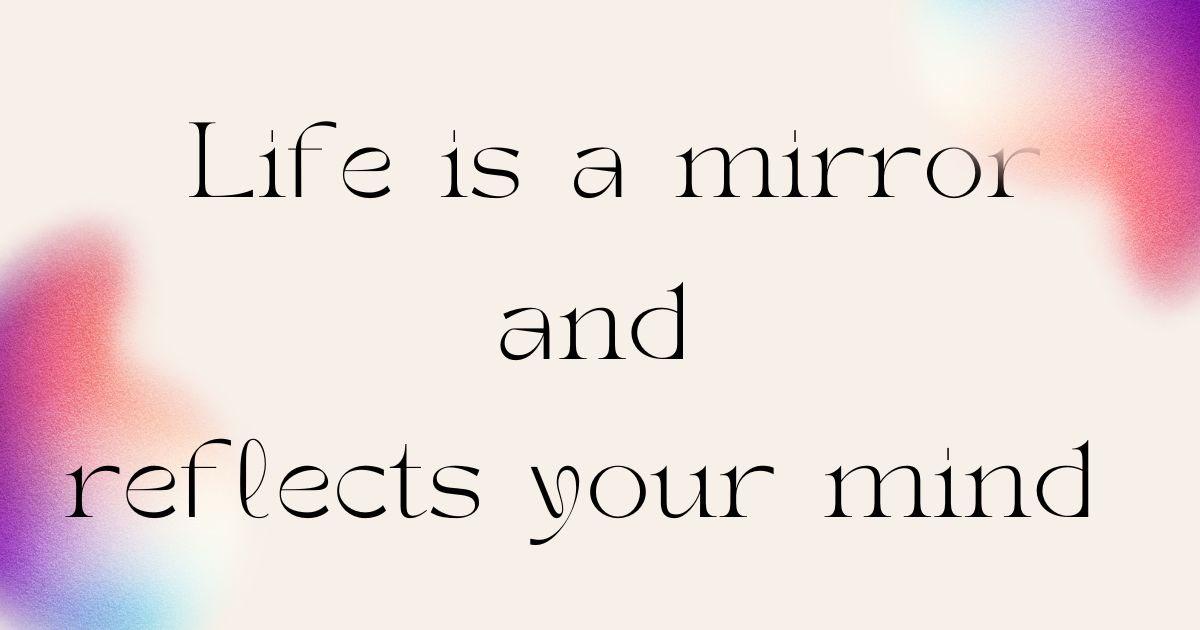世界はすべて自分しだい——ヨガ哲学とアドラー心理学から学ぶ
あなたは人生、思い通りに生きられていると感じますか?
「自分の人生、思い通りにできている♪」「自分の願いを叶えて生きているっ!!」と思える人ってどのくらいいるのでしょう?
「人生は自分の考え方次第で変わる」とよく言われますが、本当にそうなのでしょうか?
今回は、ヨガ哲学と心理学の両面からこれについて考察してみたいと思います。
ヨガ哲学とアドラー心理学の視点から考えると、私たちの目の前にある世界は、自分の心の状態や思考のクセによって形作られていることがわかります。
具体的にどういうことなのか、現実的な例を交えながら見ていきましょう。
ヨガ哲学とは?——心が世界を映し出す
ヨガはエクササイズ・体の鍛錬・フィジカル要素としての効果だけではなく、ヨガ哲学という心と体の調和を通じ、より良い生き方を目指す思想としての役割があります。
ヨガ哲学のその根本には、「心は世界を映す鏡のようなもの」という考えがあります。
たとえば、朝からイライラしていると、通勤途中の些細な出来事(電車の遅延、他人の態度)がすべてストレスの原因に思えてしまいます。でも、同じ状況でも気分が良いときは、さほど気にならないか、むしろ「ちょっとしたハプニング」と楽しめたりしますよね。
これは、外の世界が変わったのではなく、自分の内面が変わることで見え方が変わるというヨガ哲学の考え方と一致しています。
外界のすべてがあなたの思考(想念)と心理的態度に基づいている。世界はすべてあなた自身の投影物だ。あなたの評価はまたたく間に変わる。昨日は「恋人」だった人が、今日は「見るのも嫌」かもしれない。
このことを忘れずにいるならば、あなたは外的な事象にそれほど重きを置かなくなるだろう。ヨーガが外界の変革についてあまりこだわらないのそのためだ。
『インテグラル・ヨーガ パタンジャリのヨーガ・スートラ』より
世界はすべて自分自身の投影物 という思想はこちらの記事も参考に⬇️
ヨガの教え:「古代教典の解釈」
ヨガの根本教典であるヨーガ・スートラの中でも、「物事をどう捉えるか」が大切だと説かれています。例えば、
- サントーシャ(知足):今の状況に満足することが幸せにつながる
- アパリグラハ(不貪):必要以上に執着しないことで心が自由になる
無いものばかりに目を向けていると幸せを感じられないが、今あるものに目を向け満足すると幸せにつながるというワケです。
恋人や家族、持ち物や肩書きなどに執着していると心がそこに縛られていることになります。あなたの自由を決めるのはあなた次第であり、執着をしないことであなたの心の自由が得られるのです。
このように、私たちの心のあり方が、見える世界を決めているのです。

アドラー心理学とは?——すべての出来事は「解釈次第」
アドラー心理学 聞いたことはありますか?
アドラー心理学は、オーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した理論で、「人は自分の捉え方次第で人生を変えられる」と考えます。
人間関係や人生を生きやすくするための教えが豊富にあり、個人的な悩み、人生の悩みに対してヒントをたくさんくれるような個人心理学です。
「人生の悩みは人間関係にある」と説いたアドラー心理学のブームが起こり、『嫌われる勇気』を始めとしてたくさんの本が刊行されています。
『嫌われる勇気』という斬新なタイトルを聞いたことがある人や、読んだことがある人もいるのでは??
こちらの本もとても面白く、テンポよく対話形式で進む本なのでアドラー心理学を理解するのにとても役立ちます。こちらも何回も読むことで理解が進みます。アドラー心理学とヨガ哲学にはとても似通った部分もあり、とても興味深いなあと思って読みふけってしまいます。
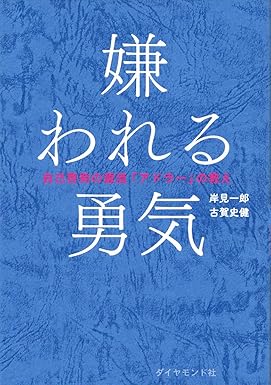
嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
アドラー心理学とヨガ哲学の共通する考えについても、書きたいことが膨らんでいますので、また別記事にて掲載したいと思います。
そんなアドラー心理学からみると例えば、仕事で上司に注意されたとき、
- 「自分はダメな人間だ」と解釈すると、自信をなくして落ち込む。
- 「機嫌が悪くて八つ当たりでしょ、嫌なやつ!」と怒りの感情を持ち続ける。
- 「指摘されないと気づけなかった。クライアントに提出する前でよかった」と安堵する。
- 「同じ失敗はしない!成長のチャンスだ」と解釈すると、モチベーションが上がる。
同じ出来事でも、自分の受け取り方次第で、その後の行動や感情がまったく変わるのです。

アドラーの教え:「課題の分離」
アドラー心理学では、「他人の評価は自分の課題ではない」と考えます。
上司が自分のことを「こんなこともミス無くできない部下」と思っているか、「成長の余地がある部下」と思っているかどうか、心情の本当のところなんて、こちらには判らないことです。
つまり、上司がどう思うかは上司の課題であり、自分は「改善できる部分を直せばいい」と割り切れば、無駄に悩まずに済みます。
目の前の世界を変える方法
例1:人間関係を良くしたい
【状況】 職場で上司や同僚とうまくいかない。
【視点の転換】
- ヨガ哲学:相手の言動に左右されるのではなく、自分の内面を整える。
- →「相手を変えよう」とするのではなく、自分が穏やかに接することで関係性が変わる。
- アドラー心理学:他人の反応は相手の課題。
- →「相手がどう思うか」ではなく、「自分はどうありたいか」にフォーカスする。
▶ 結果:無駄なストレスが減り、関係が自然と改善する。
例2:仕事での評価を気にしすぎる
【状況】 上司や同僚の評価が気になって、プレゼンが苦手。
【視点の転換】
- ヨガ哲学:「結果に執着しない」(アパリグラハ)。
- →「評価されるかどうかではなく、自分がベストを尽くせばOK」と考える。
- アドラー心理学:「承認欲求を手放す」。
- →「誰かに認められなくても、自分の成長に意識を向ける」
▶ 結果:緊張が減り、プレゼンがスムーズにできるようになる。

まとめ:目の前の世界は、自分の心が決める
ヨガ哲学とアドラー心理学は、「外の世界を変えようとするのではなく、自分の捉え方を変えることが大事」という共通の考え方を持っています。
ヨガ哲学を学んでいる最中で、こんな言葉を頂いたこともあります。
「人を変えようとするのではなく、自分が変わることで静かなマインドは訪れる」と。
ものごとが上手くいかない時。何かに満足していない時って。つい他人のせいにしがちですよね。自分のせいじゃない、他人のせいにしたい症候群…?🥲
でも、それじゃあずっと不満を抱えたまま過ごしていくことになりますね。今の現状が自分の責任だとしたら、不満ばっかり言っても始まらない、と気づけるワケです。
自分に発破をかけるとしたら、ちょっと乱暴な言い方ですが「言い訳無用!今の状況は全て自分が選んだ結果」と鼓舞してあげましょう。
もっと優しく励ましたい場合は「目の前の世界を変えたいなら、まずは自分の心の持ち方を変えてみるか」と自分に言い聞かせてみてはどうでしょう?
私自身にも何度も言い聞かせたいと思います。
『目の前の世界は全て自分の心がつくっている』『世界は自分の心を映し出す鏡』、と。